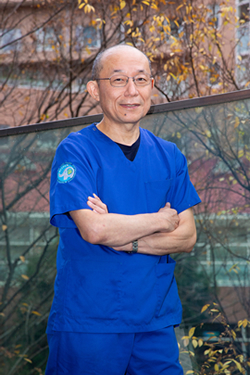
|
国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 鈴木康之統括部長 「子どもは小さな大人ではない」 |
■ 技術や知識、経験の少なさを痛感
鈴木氏が医師の道に進もうと決断したのは高校生のとき。父が内科と小児科の開業医だったため、医師は進路の選択肢の一つではあったものの、決定的なものではなかった。迷う鈴木氏の背中を押したのが高校の教師だった。鈴木氏に医師として活躍している複数の卒業生への訪問を用意してくれた。「先輩たちの話は心惹かれるものがありましたが、それ以上に印象的だったのが振る舞いです。とても素晴らしく、父とはまた違う憧れを抱きました」。
東邦大学医学部時代は弓道に熱中。卒業後、小児科への入局を選んだが、それには3つの理由があった。一つめは父親が内科系だったこと、二つめは子どもが好きだったこと、三つめは当時、小児科の中山健太郎教授が指導の厳しさで有名だったことだ。中山氏は同大学医学部教育開発室(現医学教育センター)の初代室長として臨床能力に優れた医師の育成に力を注いでいた。中山氏の厳しい指導を求めて入局した鈴木氏だったが、中山氏は脳卒中に倒れ、十分な指導を受ける機会はあまりなかった。代わりに、中山教授の下で働いていた先輩たちに一から徹底的に仕込まれた。
例えば、救急外来を担当していたとき、夜中に30人、40人と小児が搬送されてきた。熱発、痙攣、脱水・下痢、喘息など症状はさまざまだ。一睡もせずに対応しなければならない。しかも、当時は検査も自分たちが行わなければならなかった。「採血して白血球の数を数えたり、採尿を遠心分離して顕微鏡で観察したり、痙攣症状で髄膜炎が疑われると採取した脳脊髄液を染色し白血球数や細菌の形態を調べたり。大変だったけれど、とても良い経験になりました」と振り返る。
一方で、悲しく、悔しい思いもたくさんした。診ていた重症の小児患者が、突然具合が悪くなり命を落とすこともしばしばあった。「そのたびに技術や知識、経験の少なさを痛感しました」。
なんとかして小さな命を救いたいとの思いで悶々としている鈴木氏に、当時の教授が呼吸や循環の管理ができるようになるからと、自身が以前院長を務めていた都立八王子小児病院(2010年統合のため廃止)の麻酔科に行くことを勧めた。これは鈴木氏に「麻酔」という自身にとって新たな知識を身につけられる絶好の機会となった。
■ 病院の小児科医として生きる覚悟
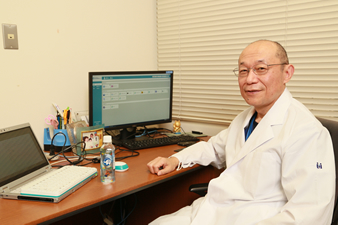 「麻酔は小児科で学んだこととは全く違いました。知らないことだらけで、もっと勉強しなければと逆に奮い立ちました」
「麻酔は小児科で学んだこととは全く違いました。知らないことだらけで、もっと勉強しなければと逆に奮い立ちました」
無我夢中で麻酔を学んだ鈴木氏は半年後に大学の小児科に戻り、NICUを担当した。2年が過ぎた頃、再び学びへの欲が出てきた。「もっといろいろな重症の小児患者を診たい」。国立小児病院麻酔科に宮坂勝之というとても優秀な先生がいると耳にした。ぜひこの先生について学びを深めたい――。こう思った鈴木氏は教授に願い出て、同病院で麻酔科レジデントとして勤務できることになった。
「宮坂先生の知識量と発想力は膨大でした。最初にご指導を受けたのは輸液・点滴です。先生は、『米国では輸液や点滴を専門にしている看護師がいる。日本の小児の重症患者の医療は遅れている』とよくおっしゃっていました。小児患者にとって何が一番大事で優先すべきか、患者中心の医療、チーム医療の重要性を教わりました。また、重症な小児患者に適した輸液ポンプ、人工呼吸器、モニターなどの医療機器の開発に奮闘されていました」
宮坂氏の下で充実した日々を過ごしていたとき、鈴木氏に悲しい出来事が起こった。開業医であった父が脳出血で倒れたのだ。幸い命はとりとめたが、伊豆の病院でリハビリ治療を受けることになった。父が再び診療に戻るまでと、鈴木氏は定期的に実家の医院で診療に当たった。しかしリハビリの甲斐なく、9カ月後父は逝去。そして出てきたのが医院の承継問題だった。
「その頃、麻酔やICUの診療が楽しくて仕方がなくなっていました。かといって、父がせっかく開いた医院を閉じることは、父にも、また父の元に長年通ってくださった患者さんたちにも申し訳ないし、どうしようかと随分迷いました」。そうしたとき、思ってもみなかった打診があった。カナダのトロント小児病院への留学だ。
「こんなチャンスは二度と来ない」。開業医ではなく、小児病院の麻酔科医として生きる覚悟が決まった。
■ 小児一人ひとりに合わせて麻酔を微調整
「でも、私の留学はなんちゃって留学でした」と笑う鈴木氏だが、もちろんけっしてそんなことはない。まずはICUで学んだ後、麻酔科の研究室でパルスオキシメーターの研究を行った。また、その研究室の部長が日本で開発された吸入麻酔薬セボフルランの臨床データを取っていた関係から、麻酔薬が脳や血液にどの程度溶けるかを調べる研究にも携わることができた。
1年余りにわたる留学を終えて日本に帰国して取りかかったのが、セボフルランの腎毒性についての動物実験だった。そして懸念されていた腎毒性は、「認められない」との結論を得る。
こうして麻酔に精通した鈴木氏は、小児麻酔について次のように話す。
「小児と一言でいっても、体重が350gほどのお子さんから、100kg近くあるお子さんまでいて、体重だけでも300倍くらい差があります。加えて、発達段階も個々人で異なりますし、同じ年齢、同じ体重でも麻酔薬の反応には個人差があり、バリエーションがとても豊かです。それだけに、投与量や速度など大人以上に細かな調整が必要です。半面、反応がとても速いのも小児麻酔の特徴です。だから面白いのです」
■ 無限の未来を守ることと家族ケア
小児科医そして麻酔科医として歩んできた40年の間、たくさんの子どもたちと触れ合ってきた。残念ながら亡くなった患者もいるが、元気になって将来が拓けた患者も少なくない。3年前には思いがけない連絡が入った。
国立小児病院時代のこと。のどに血管腫ができた男児が他の病院から転院してきた。入院当日の夜、血管腫が腫れて窒息状態に陥った。鈴木氏はすぐに蘇生して挿管し、気管切開して血管腫を除去。その後、元気に退院することができた。連絡をくれたのはその重症児だった。
「彼は医学部の学生になっていました。将来、救急医、小児科医になりたいから当センターの急性期医療を見学に来たいというのです。一度は命に危険が迫った子どもが無事成長して、しかも小児科医を目指しているという話を聞いて、本当に嬉しかったです。無限の未来を守るのが小児に携わる医療者の役目だと改めて強く思いました」
もう一つ、我々には重要な役目があると鈴木氏は言う。家族のケアだ。
「子どもが病気だと、家族も病んできます。また、家族は病気の子ばかりに気が取られがちなので、その他の兄弟のケアも必要です」。こう話す鈴木氏が常に心掛けているのが家族と信頼関係を築くことだ。そのためには「まず、相手の話によく耳を傾け、難しい説明には丁寧に時間をかけて話すことが大切」と強調する。
ただし、家族に過剰な期待を持たせてもいけないし、かといって絶望的な思いをさせてもよくない。その塩梅にベテランとなった今でも細心の注意を払っている。
■ 子どもに使える薬や機器の開発を


公式キャラクター
「いくぞうくん」
小児医療が直面している課題は多い。その一つが薬剤で、子どもに使用される薬の多くが適応外使用となっている。例えば、麻酔薬の場合、年間200万人ぐらいに投与されているが、小児はその10分の1。数が少なければ治験に時間がかかり、当然費用も高くなる。そのため製薬会社は小児用薬の開発に慎重にならざるをえない。医療機器についても子どもに適したものがあまりにも少ない。
鈴木氏は、製薬会社や医療機器メーカーの担当者にいつもこう話す。「子どもに使える精度があれば大人にも使える。子どもに使えるものを開発してほしい」。
鈴木氏は最後に噛みしめるかのように、「自分の周りのひとに恵まれた人生を送ってこられたと思います。患者さんやご家族からもたくさんのことを教えていただきました。そうした方々のお陰で、今日の私があるといっても過言ではありません。本当にありがたいことです」と語った。
今も重症患者の治療に向かうときには自然とアドレナリンが出てくるという鈴木氏。子どもの未来を摘み取ろうとする病と全力で闘おうとする医師の姿がそこにある。
取材・文/荻 和子 撮影/轟 美津子
