
|
名古屋大学大学院医学系研究科 病態外科学講座心臓外科学 六鹿雅登教授 この9月、ラグビーの世界一を決めるワールドカップフランス大会を心待ちにしていた元ラガーマンは多かったのではないだろうか。日本胸部外科学会ラグビー部のメンバーも10月の同学会定期学術集会開催の地、仙台で久しぶりに集まって大いにもりあがった。その中に2022年、名古屋大学大学院医学系研究科病態外科学講座心臓外科学教授に就任した六鹿雅登氏の姿もあった。 |
■ Once a cardiac surgeon, always a cardiac surgeon
六鹿氏の高校生活はラグビー一色。クラブ引退後、運動から勉強に切り替え、父と同じ医師の道を進もうと名古屋大学医学部を受験したが不合格。浪人生活を経て、名古屋大学に念願の合格を果たした。
名古屋大学の新入生は入学手続きの日、クラブやサークルのメンバーが新入生を勧誘する「地獄の花道」を通らなくてはならない。その洗礼を受ける六鹿氏を待ち受けていたのは高校のラグビー部の先輩だった。「入学前から全学ラグビー部の練習に参加していました。大学4年間は“しっかり”ラグビーをしましたよ」と楽しそうに話す六鹿氏は、4年次にはキャプテンも務めた。
5年次からは部活動から勉強に軸足を移した六鹿氏が卒業後に初期研修を行ったのは、大垣市民病院だった。救急患者が多いことで知られ、毎日無我夢中で患者と向き合った。
元々父と同じ脳外科に進むつもりでいたが、同じ外科ではあるが父とは異なる選択をした六鹿氏。そのきっかけとなったのは同病院の心臓外科部長(当時)だった玉木修治氏による大動脈解離手術だった。「出血もなく次々と処置していく玉木先生の手術は本当に見事でした。心臓外科とはなんとダイナミックなのだろうと思いました」。
玉木氏は、脳外科に進みたいという六鹿氏に、英語のことわざ「Once a beggar, always a beggar」をもじって「Once a cardiac surgeon, always a cardiac surgeon」とよく言っていたという。六鹿氏は玉木氏の手術を見て、この言葉の意味がストンと腑に落ちた。「以来、私は心臓外科の魅力にはまっています。ただ、途中で心臓外科から離れる人もいるので、みんながみんなそうでもないようですが」と苦笑する。
■ 2年間のカナダ留学で人工心臓や心臓移植を多数経験
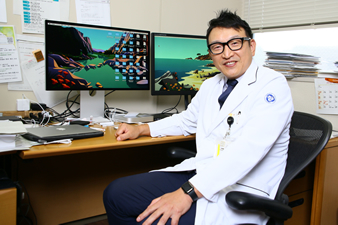 六鹿氏が指導を受けた玉木氏は心臓外科の中でも特に小児に力を入れていた。その影響で六鹿氏は海外で小児心臓外科をもっと学びたいと思うようになった。そのチャンスは10年余りいた大垣市民病院を離れ、名古屋大学心臓外科医員として帰局して間もなく訪れた。
六鹿氏が指導を受けた玉木氏は心臓外科の中でも特に小児に力を入れていた。その影響で六鹿氏は海外で小児心臓外科をもっと学びたいと思うようになった。そのチャンスは10年余りいた大垣市民病院を離れ、名古屋大学心臓外科医員として帰局して間もなく訪れた。
当時の心臓外科教授の上田裕一氏の計らいで、カナダ・エドモントンにあるアルバータ大学小児心臓外科教授アイヴァン・レベイカ(Ivan Rebeyka)氏のもとでクリニカルフェローとしての留学が実現したのだ。
「エドモントンはカナダ西部にあり、冬はマイナス20℃まで下がるような寒いところです。でも、人はとても温かく優しい。環境も含めて、すぐに気に入りました」
日本とは桁違いの手術数を持つ病院だけあって、六鹿氏は数多くの手術をこなしていった。「日本と大きく異なるのは、仕事が細分化、合理化されており手術に専念できることです。また、手術室専属のベテラン看護師がいてセットアップが早く、手術のスピード感が全く違いました」と、当時の驚きを話す。
同病院には、南アフリカやサウジアラビア、インドなど世界各国からレジデントやクリニカルフェローが多く来ていた。「特にインド人のフェローはオーストラリアやイギリスの病院にも留学経験があり、小児の手術がとても上手でした。親切にいろいろ教えてくれて、彼とは家族ぐるみの付き合いをしました」。
小児心臓外科のフェローの期間は1年のみだったが、もう1年エドモントンに残りたいと強く望んだ六鹿氏は、次のポストをフェロー開始後すぐに探し始めた。
一方、名古屋大ではその頃、心臓移植実施施設の認定(後にまず必要となるのは植込型補助人工心臓実施施設であったが)を取る準備が進められていた。例えば、移植実施施設認定には移植のフェローがいることが条件の一つにある。そうした状況も後押しし、六鹿氏は人工心臓や移植を行うクリニカルフェローのポストの面接を受け、さらに1年エドモントンに残れることになった。
こうして勝ち取った留学2年目は、成人や小児の心臓および肺移植のドナー採取、移植手術、植込型人工心臓手術に携わるという、以前にもまして多忙な日々を送ることになった。カナダが協定を結んでいた米国にもしばしばドナー採取に行ったという。
「プライベートジェットで行くのですが、飛行機の中で入国審査を受け、到着したらそのまま病院へ行くのです。心臓を取り出したら、また飛行機に乗ってとんぼ返りして、患者さんに移植手術を行う。この往復が短期間に3回ほど続いたこともありました」
また、英語とフランス語を公用語とするカナダならではの珍しい経験もした。
「小児の心臓を取りにフランス語圏の病院に行ったのですが、看護師がフランス語しかしゃべれないのです。肝臓の先生が通訳をしてくれながら採取手術をしました。訪れた先で初めて顔を合わせる母語の異なる麻酔科医や看護師らとすぐにチームを結成し、コミュニケーションを取りながら心臓を採取して帰ってくるのはとても良い経験になりました」
■ 移植患者が普通の生活を送れる心臓外科医の喜び
 2年間の充実した留学生活を終え、2011年に帰国。ちょうどその年、植込型補助人工心臓が保険償還され、いよいよ名古屋大学でもその実施施設認定を受けるために本格的に動き出した。それには体外式補助人工心臓を3か月以上管理しなければならない。そのとき同大が選んだのは海外で広く行われた遠心ポンプによる体外式人工心臓治療だった。1年間管理し、無事に離脱に成功した。この症例により2013年、植込型補助人工心臓実施施設認定を取得できた。その後、植込型人工心臓は徐々に増えていき、心臓移植実施施設認定取得の必要性がより高まり、2016年に申請、その年の暮れ、名古屋大学は国内10番目となる認定を取得した。
2年間の充実した留学生活を終え、2011年に帰国。ちょうどその年、植込型補助人工心臓が保険償還され、いよいよ名古屋大学でもその実施施設認定を受けるために本格的に動き出した。それには体外式補助人工心臓を3か月以上管理しなければならない。そのとき同大が選んだのは海外で広く行われた遠心ポンプによる体外式人工心臓治療だった。1年間管理し、無事に離脱に成功した。この症例により2013年、植込型補助人工心臓実施施設認定を取得できた。その後、植込型人工心臓は徐々に増えていき、心臓移植実施施設認定取得の必要性がより高まり、2016年に申請、その年の暮れ、名古屋大学は国内10番目となる認定を取得した。
翌年4月、同大で中部地区初の心臓移植が行われた。このときの執刀医は碓氷章彦教授(当時)で六鹿氏は第1助手だったが、2例目は六鹿氏が執刀した。その患者は大学生のときに重症心不全を発症し、中退を余儀なくされた20代の男性だった。植込型人工心臓を装着後、仕事をしたいとの本人の希望もあり、集中治療室の補助看護師となった。植込型人工心臓装着の約4年後に心臓移植を受け、その後6年ほど経った今は、当時の仕事先で仲良くなった看護師がつくった高齢者介護施設で元気に働いているという。
「先日、外来で病院に来たとき会ったのですが、『今度結婚するかも』とニコニコして話してくれました。普通の生活を送れていることが心から嬉しい」
重症心不全の患者にとって普通の生活を送れることは元気になった証だ。それを手に入れるまでに大変な思いをしたことを、多くの患者を診てきた六鹿氏は痛いほどわかっている。だからこそ、もっと医療技術のレベルを高めなくてはと強く思うのだ。
■ アカデミックアクティビティをもっと活発に
 六鹿氏は2022年、碓氷教授の後を引き継いで教授に就任した。
六鹿氏は2022年、碓氷教授の後を引き継いで教授に就任した。
今、社会は大きな変革期に来ている。医学界も例外ではない。例えば医学部に進学する女性の割合は増えているが、心臓外科は時間的な拘束が長くなりがちなため、敬遠されやすい。「当医局も、女性医師が結婚したり子どもができたりしても働き続けられる職場環境をつくっていかなければなりません」と語る六鹿氏だが、よく言われる外科医の希望者減少については楽観的だ。「先日、日本心臓血管外科学会が2日間のサマースクールを開催しました。1日目は座学、2日は豚の心臓を使って手術の練習をする内容で、希望者が殺到したそうです。外科好きは常に一定数いると思います」。
また、最新の医療機器も積極的に導入していかなければならない。同大医学部附属病院では2018年より3D内視鏡による僧帽弁形成術を開始し、僧帽弁置換術、大動脈置換術など、徐々に適応を広げてきた。さらに2023年1月にはロボット支援下手術を導入し、8月までにすでに15例を実施した。
「私が医局に入った頃は、ロボットで心臓手術をするなんて想像もしませんでした。まさか自分たちが使う時代が来るなんて驚きです」と話す氏は、こう続ける。「私たち人間の技術が今後、飛躍的に伸びることはないでしょう。しかし、機械のテクニックはその可能性が大いにあります。AIが機械に搭載され、学習するようになれば、術者は不要になるかもしれません。どこまで進んでいくのか、期待しながら見守っていきたい」。
一つ、六鹿氏が気になっていることがある。病態外科学講座のアカデミックアクティビティをもっと高くすることだ。施設が誇るテーマのひとつが、植込型補助人工心臓治療におけるドライブラインの感染制御である。同大での感染率は世界的にも低い。ドライブラインの貫通方法の工夫や入院時からの患者への教育などが効果を上げているからだと六鹿氏は評価する。「植込型補助人工心臓治療の管理に関しては国内外に向けてどんどん発表していきたい」と意気込む。
明治大学ラグビー部を67年間率いた北島忠治監督は「前へ」と言い続けた。六鹿氏も壁にぶつかったとき、この言葉を自分に言い聞かせるという。「ラグビーで勝つためには前に進むしかありません。人生も同じ。前に進まなければ壁を乗り越えることはできないのです」。青春の7年間をラグビーに明け暮れた元ラガーマンは、力強くこう言い切った。
取材・文/荻 和子 撮影/轟 美津子
