
|
東京大学医科学研究所附属病院 セルプロセッシング・輸血部/検査部 長村登紀子准教授 “リケジョ”という言葉がマスコミに登場する前から医師の道を選び、 |
■ 隣人の影響で医師を目指す
 長村氏が生まれ育ったのは山口県中央部にある小郡(おごおり)町(現山口市)。昔から山陽の宿場町として栄えた静かな町だ。「自慢ではありませんが、体育の成績だけは小学校からずっとよかった。家族は信じてくれませんが(笑)」と自身が認めるほどの運動少女だった長村氏に新しい興味をもたせてくれたのは、高校教師をしていた父親だった。「父が鶴亀算を、連立方程式で解く方法を教えてくれたのです。鶴亀算ではうまく解けなかったのに、方程式ではスラスラと答えが出せて、数学って面白いなと思いました」。
長村氏が生まれ育ったのは山口県中央部にある小郡(おごおり)町(現山口市)。昔から山陽の宿場町として栄えた静かな町だ。「自慢ではありませんが、体育の成績だけは小学校からずっとよかった。家族は信じてくれませんが(笑)」と自身が認めるほどの運動少女だった長村氏に新しい興味をもたせてくれたのは、高校教師をしていた父親だった。「父が鶴亀算を、連立方程式で解く方法を教えてくれたのです。鶴亀算ではうまく解けなかったのに、方程式ではスラスラと答えが出せて、数学って面白いなと思いました」。
数学を含めて理系が好きになった少女は、高校は理数科へ進学した。理数科は40人1クラスのみで、そのうち女子生徒は4人だけだった。「人数が少ない分、仲が良かったですね。クラスメートに誘われてESSに入部したのですが、いつもは英語はそっちのけでトランプばかりしていて、文化祭の時だけ英語劇をしていました」と懐かしむ。
そんな長村氏には、子どもの頃からずっと憧れている職業があった。きっかけをつくったのは実家の隣人だった。
長村氏の実家は病院の前にあり、実家の隣にその病院に勤務する医師夫婦が住んでいた。彼らにはまだ子どもがおらず、長村氏をわが子のようにかわいがってくれた。「その先生が子どもの目にかっこよく映り、いつしか医者になりたいなと思うようになったのです」。
さらに進路について父と相談したとき、父から思いもよらない話を聞かされた。「父は医師になりたくて医学部に進んだけれど、経済的な理由から退学せざるを得なかったと明かしてくれたのです。きっと父は断腸の思いで医師になる道を諦めたと思います。父の分も頑張って、医師になろうと改めて決意しました」。
小郡から山陰線1本で行ける島根医科大学(現島根大学医学部)に進学した理系少女は、夢を実現させる第一歩を歩みはじめた。
■ 山口大学医学部から血液の真髄、医科研へ
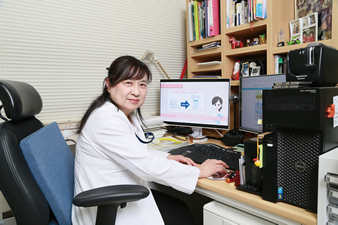 長村氏は専門にする診療科も入学時から血液内科と決めていた。「私をかわいがってくださった隣人の先生が血液内科医だったので」。血液内科(第一内科)に入局したが、翌年、実家に近い山口大学医学部血液内科(第三内科)に移った。そのことがのちの長村氏の人生に大きな転機をもたらすことになる。
長村氏は専門にする診療科も入学時から血液内科と決めていた。「私をかわいがってくださった隣人の先生が血液内科医だったので」。血液内科(第一内科)に入局したが、翌年、実家に近い山口大学医学部血液内科(第三内科)に移った。そのことがのちの長村氏の人生に大きな転機をもたらすことになる。
山口大学医学部第三内科にはかつて、故・三輪史朗氏が教授として在籍したことがあった。三輪氏は米国留学中に血液中のピルビン酸キナーゼ欠乏による溶血性貧血患者を世界で初めて発見した血液学の大家だ。その三輪氏が山口大学から東京大学医科学研究所(以下、医科研)に移ったことから山口大学には医科研とのルートができていた。
ある日、長村氏は血液内科の先輩からこう言い渡された。「君は医科研に行って頑張りなさい」。
長村氏は、「若かったから不安は全くなかったですね。医科研は血液学の真髄のところ。むしろ、ワクワクした気持ちで上京しました」と医科研へ向かった当時を振り返る。
■ 2人の子どもとともに夫に帯同して米国留学
医科研で待っていたのは夜遅くまで実験をし、臨床もこなすという多忙な日々だった。「こんな生活を続けていたら長生きできないかもしれないと思ったこともありました。でも、そんな不安以上に、毎日が刺激的で楽しかったですね」。日本の造血幹細胞移植を牽引していた故・浅野茂隆教授に、夜中にラーメンや焼き肉を食べに連れていってもらったことも今では忘れられない思い出の一つだ。
浅野教授の下にいた岡本真一郎氏(前慶應義塾大学医学部血液内科教授)から造血幹細胞移植を学び、東條有伸教授(現東京医科歯科大学副理事・副学長)に基礎研究を学び、慢性骨髄性白血病をテーマに臨床と研究にいそしんだ。その成果は4年も経たないうちに論文博士の学位取得として結実した。
その後、東京大学医学部免疫学教室で免疫学を学び、再び医科研に戻ってきた。この間、医科研の同僚と結婚し、第一子が誕生するというプライベートにおいても大きな変化があった。
長村氏の言葉を借りれば“計画的”に年子で第二子を出産し、その半年後にはFDA(米国食品医薬品局)に留学する夫に帯同して渡米した。このとき長村氏自身もNIH(米国国立衛生研究所)で研究するアポイントメントを取り付けていたが、ビザの関係で給料をもらえる身分になかったため、NIHの事務に面談することとなった。その際、NIHの研究室のボス、尾里啓子先生からこうアドバイスされた。「オフィサーとの面談時には、自分は働きたい、研究をしたいと猛アピールしたほうがいい」。当時、NIHには日本人の女医が何人も入っていたが、その多くが子育てで忙しいので少し研究室の雰囲気を味わってみたいという手伝いのような感じでの研究参加だった。そのアドバイスを聞いたとき長村氏は「日本人女医の姿勢が問われている」と思ったという。
助言にしたがって猛アピールしたかいあり、研究者として働き給料を得ることができた。一方、電話をかけまくり、2人の子どもは夕方6時までナーサリーに預ける段取りを整えた。
留学に関して、長村氏には一つ残念だったことがある。留学後すぐにNIHでマウスの実験をしたかったが、日本人の男性研究者から「子育てもあるので時間的に無理でしょう」と言われ、受け入れたことだ。「ホントにいらぬお世話ですよね」。今でこそ笑ってこう話す長村氏だが、おそらくそのときは何ともいえない口惜しさを覚えたに違いない。
■ 細胞を使う側から細胞を作る側へシフト
2000年9月、2年半の米国生活を終え帰国。古巣である医科研に戻り、入ったのが細胞プロセッシング寄付研究部門だ。同部門は、当時著しい進展を遂げていた細胞治療をさらに促進させる目的で1995年に開設され、97年に「東京臍帯血バンク」を立ち上げていた。また、98年には医科研附属病院でわが国初の成人への臍帯血移植が成功を収めるなど、臍帯血移植は著しい伸展をみせていた。さらに同部門は、2000年頃からは胎盤や臍帯を用いた再生を目指していた。
長村氏は高橋恒夫客員教授に師事し、同部門の東京臍帯血バンクを担当、品質システムの国際規格「ISO9001:2000」の認証を取得したり、品質管理に努めたりした(東京臍帯血バンクは2014年3月31日で終了)。それ以降、細胞を「使う側」から細胞を「作る側」へと立場を変えて今日に至っている。
その後、医科研附属病院セルプロセッシング・輸血部に異動し、ここで間葉系細胞(MSC)の可能性を知る。「それまで私は再生医療はやらないと決めていました。血液内科医としての矜持、というのでしょうか。ところがその頃、MSCが骨や脂肪、軟骨や神経系細胞、肝臓細胞などに分化する能力をもっているだけでなく、過剰な免疫反応を抑制する作用があることがわかってきました。『あ、MSCも血液じゃないか』と思ったのです。免疫系疾患の治療に使えると考え、MSCと真正面から向き合いはじめました」。
MSCは骨髄由来のものが先行的に使われていたが、長村氏は、ドナーに身体的負担のない臍帯に注目し、基礎検討を進め、2017年「東大医科研病院臍帯血・臍帯バンク」を設立した。
現在、医科研臍帯血・臍帯バンクが提供したMSCを用いて、重症急性移植片対宿主病(GVHD)や脳性麻痺などへの治験が進められている。2020年には、自身の研究データをベースにした新型コロナウイルス感染症に伴う急性呼吸窮迫症候群(ARDS)に対する臍帯由来MSCを用いた企業治験も始まるなど、活躍の場が広がっている。
■ 子どもたちの励ましの言葉と仕事への情熱がパワーの源
 長村氏が手にとる凍結保存容器2.5mLタイプ「セルキュア®」(右)は、《「セルキュア」シリーズ》として、2021年度グッドデザイン賞受賞対象の中で、審査委員会により特に高い評価を得た100件に選ばれた。左は、開発中の25mLタイプ「セルキュアムーン®」。 |
|

|
製品の詳細は こちらのQRコードから ご覧ください。 |
|
2021年度 グッドデザイン賞受賞 ・ベスト100選出 |

|
しかし、坂道を登るのをやめようと思ったことは一度もない。「子どもたちからの『頑張って』という言葉と、なんと言っても『この仕事が大好き』という思いが力になりました」。
最近、嬉しいニュースが飛び込んできた。長村氏らから助言を受けながら弊社が開発した凍結保存バッグ「セルキュア」シリーズが2021年度グッドデザイン賞ベスト100を受賞したのだ。
さらに10月には、医科研の地下に最新設備を揃えた細胞調製室が完成した。ここは、臍帯由来間葉系細胞製品の原料を培養し、企業や研究機関へ良質な細胞を供給するための核になるところだ。同時に、研究用や臨床試験用の細胞を製造することで、医科研における研究の発展に大いに貢献することが見込まれている。
今でも患者を診るフィジシャンであると同時に、研究を続けるサイエンティストでもある長村氏は、力強くこう言い切った。「私はこれからもフィジシャン・サイエンティストの人であり続けたい」。
取材・文/荻 和子 撮影/轟 美津子
