
|
広島大学大学院 医系科学研究科 外科学 髙橋 信也 教授 広島人はひときわ郷土愛が強いという。 |
■ 今、自分のやるべきことは何か
髙橋氏が心臓外科医を志したのは、医学部5年生のときだった。ポリクリで目にした、当時の外科学助教授・末田泰二郎氏による弓部大動脈置換術に、心をわしづかみにされたという。体外循環中に体温を徐々に下げていき、心臓を停止させ、その間に大動脈を置換、再び体温を上げていくと心臓が元のように動きだすという低体温循環停止法による手術だった。髙橋氏はそのダイナミックさに圧倒された。「これしかない!」。医師として進むべき道が定まった。
心弾ませて入局したものの、先輩医師が執刀する心臓手術をサポートするのみの毎日。どんなふうに手術をしているか、もっと見たいと心臓をのぞき込もうとすると、途端に先輩医師からの「頭が邪魔だ。中が見えないじゃないか」という叱責が飛ぶ。そんな日々を1年余り送っていた髙橋氏に、関連病院の消化器外科から人手が足りないから来てほしいとの依頼が舞い込んだ。しかし、心臓外科以外考えたことがなかった髙橋氏は受諾を躊躇した。そのとき説得された言葉を今でもはっきりと覚えている。「外科の技量は手を動かして学ぶことができる。消化器外科なら新人医師でも手を動かすチャンスがある」。
自ら望んで行ったわけではない消化器外科だったが、まさかここでの経験がその数十年後に大いに役立つとは思いもよらなかった。
当時、消化器では腹腔鏡下での胆嚢摘出手術がスタンダードになりつつあった。また、腸の切除も腹腔鏡下で行うという動きもあった。若い髙橋氏ならモニタを見ながら手術ができるだろうと腹腔鏡手術のチャンスを与えられたのだ。「消化器外科にいた2年半ほどで、50例以上の腹腔鏡手術をさせてもらいました。そののち心臓外科でもカメラ手術が広まってきたとき、かつて同じ道具を触ったことがある経験は、私にとって大きなアドバンテージになりました」と感謝する。
消化器外科から戻ってきた髙橋氏は、心臓外科で有名な倉敷中央病院で修行を積むことになった。
ここで毎週行われていたのが抄読会だ。「前もって準備をして抄読会に臨まなくてはいけません。準備をしないで行くと、『お前は勉強する気がないのか』と先輩方からお叱りを受けるのです。忙しい中で論文を読むのはとても大変でしたが、おかげで何百という論文を読破し、一通りの手術の考え方を身に付けることができました」。ここでの経験も髙橋氏にとって貴重なものになった。
もう一つ、この抄読会は髙橋氏に大きな出会いをもたらした。「論文をずっと読んでいるうちに、イタリアのトリノ大学にカラフィオレ先生というバイパス手術や僧帽弁手術、左室形成術の名医がいることがわかりました。その先生のもとでどうしても勉強したいという思いが強くなったのです」。
夏休みを利用して渡伊。カラフィオレ氏に留学したいと直談判したところ、無給でよければ、という嬉しい返事を得た。髙橋氏は翌年の2004年、トリノへと向かった。
「倉敷中央病院の先生方も大変手術が上手ですごいと思っていましたが、カラフィオレ先生はそれに輪をかけたものすごさでした。週10~15件の手術を指導、執刀されるのです。それができるのは処置が素早いから。心臓を止めておく時間も短くてすむので、患者さんの体への負担は少なく、回復がとても早い。全く無駄のない、素晴らしい手術を毎日見られたのはこの上ない幸せでした」と当時を振り返る。
また、古代から数多くの芸術作品をつくり出してきたイタリアらしく、イタリア人医師たちがそれぞれに美学を持って、各自のスタイルで執刀しているのも面白かったという。
一方で苦い経験もした。カラフィオレ氏の手術を手伝っていたときのことだ。患者が出血を起こしたが、まもなく止血したため、髙橋氏はそのまま手術創を縫合し、患者を病棟に戻した。それを知ったカラフィオレ氏は患者をもう一度手術室に運び、手術創を確認するように命じた。「なぜこの状態で縫合したのか」とカラフィオレ氏に叱責されたとき、髙橋氏はハッとした。自分は手術の勉強ばかり気をとられていて、患者さんを治療するという医師の本来の役目を忘れかけていたのではないか──。「イタリアに来て少し浮かれていたのだと思います。以来、今、自分がやるべきことは何かを熟考するようになりました」。
■ 外科手術の技術は、スポーツに通じる
 1年間のイタリア留学を終え、広島大学に戻ってきた髙橋氏は、前教授の末田泰二郎氏にこう提案した。「欧米ではもちろんのこと、日本でもオフポンプ手術が増えつつあります。広島でも少しずつ行われてはいますが、可能なら全例オフポンプで行う努力が必要です。このようなことは、基幹病院である大学病院が先頭に立って行うべきです」。今、何をやるべきかを考え抜いて出てきた提案だった。
1年間のイタリア留学を終え、広島大学に戻ってきた髙橋氏は、前教授の末田泰二郎氏にこう提案した。「欧米ではもちろんのこと、日本でもオフポンプ手術が増えつつあります。広島でも少しずつ行われてはいますが、可能なら全例オフポンプで行う努力が必要です。このようなことは、基幹病院である大学病院が先頭に立って行うべきです」。今、何をやるべきかを考え抜いて出てきた提案だった。
最初は「エッ」と驚いていた末田教授だが、髙橋氏の提案に理解を示した。2005年の秋より症例数とオフポンプの割合を増やし、2009年には単独冠動脈バイパス術に対して100%オフポンプで行うことを達成した。
2019年8月、髙橋氏が広島大学大学院医系科学研究科外科学第5代教授に就任。それを機に、同講座はそれまでの安全第一を前提とした慎重な術式を適用するという姿勢から、そのスタンスをもう一歩踏み出し、国内で行われている術式はすべて行うという積極的な方向へと大きく転換した。
髙橋氏はスタッフたちに「当講座はこれから低侵襲手術を追求します。それが患者の身体的負担を軽減させ、早期回復につながります」と宣言した。このとき、髙橋氏はトリノ大学留学時の3、4日で嬉しそうに退院していく患者の姿を思い出していた。
以降、わずか3年の間で、髙橋氏は右小開胸の弁膜症手術や左小開胸冠動脈バイパス術、胸腔鏡下の心房細動手術など次々に低侵襲手術を導入。特に弁膜症手術においては、今では7~8割が6センチ程度の切開ですむ右小開胸になっている。
低侵襲手術をするにはスタッフたちに繰り返し練習し、手術の腕をもっと磨いてもらう必要がある。そこで教授就任後すぐに練習用道具を購入し、練習できる環境を整えた。また、スタッフたちには絶えず道具を触り、手に馴染ませるようにと伝えている。
「道具を手に持ち、重さや形を体に徹底的に覚えさせる。そうなれば道具が体の一部となって正しく動くようになります。例えば縫合針を手首だけで動かすと安定せず、組織を傷つけやすくなります。そうではなく、上腕から動かすようにすれば、腕の重みが縫合針に伝わり、安定した針の運びができます。野球のバッドを手首だけで動かしてもボールは遠くへ飛ばないのと同じです。外科はスポーツに相通じるところがあります」と語る髙橋氏の白衣のポケットには今も常になんらかの道具が入っている。
■ 困難の中に、機会あり
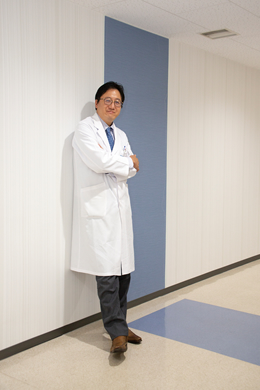
真摯に困難なほうを選ぶと、
そこに活路が開けてくる。〟
髙橋氏が最近、新たに取り組み始めたのが広島の外科医療の底上げと均質化だ。病態に対し、どこの病院でも同じ術式が提案でき、しかも一定レベルの治療を行えることを目指し、広島大学関連病院の術者を集めた勉強会を開催。また、ウエブを介しての24時間随時カンファレンスもスタートさせた。
髙橋氏の好きな言葉がある。“In the middle of difficulty lies opportunity”(困難の中に、機会あり)、物理学者アインシュタインの言葉だ。
心臓外科は患者の命に直接かかわる医療だ。厳しい局面に遭遇することが少なくない。「いくつかの対応策が考えられるとき、楽な方法を選ぶとたいてい失敗します。真摯に困難なほうを選ぶと、そこに活路が開けてきます」。これも自身の心臓外科医人生から体得した信念なのだろう。
 幼い頃からバイオリンを習っていたという髙橋氏の一番のリラックスは、音楽を聴くこと。教授室の机の下にはお気に入りのCDが400枚ほど山積みされている。夜遅く音楽を流しながら、患者のため、後輩や仲間のため、そして広島のために今すべきことを思索する髙橋氏の姿が目に浮かんでくるようだ。
幼い頃からバイオリンを習っていたという髙橋氏の一番のリラックスは、音楽を聴くこと。教授室の机の下にはお気に入りのCDが400枚ほど山積みされている。夜遅く音楽を流しながら、患者のため、後輩や仲間のため、そして広島のために今すべきことを思索する髙橋氏の姿が目に浮かんでくるようだ。
取材・文:荻和子/撮影:轟美津子
